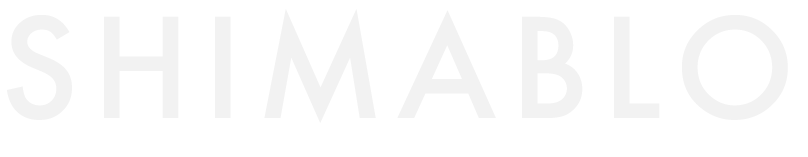- 目次 -
Toggle
ニューヨークの撮影を終え、帰国しました。
近代化の波は、美しき伝統文化を探すこと難しくさせて、おおきな課題にも直面しているように思えます。
グローバル化の中で、地域の文化、特色、伝統をアピールすることは、強固な精神、曲げない信念も必要なのかな
地域おこし協力隊:1万人
総務省は、地域創生プロジェクトとして、三大都市の住民を対象に「地域おこし協力隊」という制度を設け、今後全国に1万人規模で展開して地方活性化を目指してます。
現在は約5600人で、数年で10000人・・・倍にするとのこと。
まさに、移住戦国時代と感じずにいられません。
都会生まれ、都会育ちの自分には、地域創生・地方の溢れる魅力などを発信して語る資格など本来ある訳もありませんが…
移住戦国時代と勝手に言うのは、地域おこし協力隊という制度も、制度を利用した移住の先に、大きな歪みを生むことは、ことIT分野で募集要綱を見て気がつきます。
移住制度としては素晴らしいのですが、かなりグレーな導きの匂いがしますね。この制度、現場オペレーションとして、思うことが多々あるのです。
とりわけ、・・・
話題のDX(デジタルトランスフォーメーション)や宣伝PRのワークフローに関しては、各自治体の求人募集要項を見ているだけで・・・
危機感を感じる。
地域PRの頻度とクオリティ
危惧すべき自治体の募集要項の実例を出しましょう。
地域おこし協力隊の移住先第二位の長野県とある町。自分はとても好きな町でお世話にもなっているが故、そこでの浅はかなポンコツ募集要項「毎日動画更新ユーチューバー募集」には憤慨した。
悪気がないことが、この制度の最大の問題ですね。
- 「毎日動画更新」をしたことがない人間が
- 映像制作のワークフローを何も知らず
- その影響力を計算できずに募集している
公務員ほどクリエイティブと遠い方々はいないわけで、クリエイティブの先にあるものの責任を取るとは到底思えないですよね。
まず、地方活性化としてYouTubeは功を奏せば間違いなく良い武器となりえますが、側から見ているYouTuberが毎日動画配信していることと、地域移住者を増やすためのPR映像には、根底から性質が違う。
映像の本質が根底から違うのに、勘違いしてコテ先の更新頻度だけ模範してしまっている。
自治体の目的は、地域の魅力をドリルダウンさせなければならないはず。
毎日公開できるようなものは、レギュレーションの観点から低クオリティは避けられない。
ただでさえド田舎者が低クオリティな安いっぽい動画を作って、そんな地域には都会人として余計行きたくなくなるわけです。映像の影響力とは、良い方にも悪い方にも絶大に働くわけですから。
また、映像制作というのは、毎日更新できるようなものでは到底ない。
- 企画
- キャスティング
- 予算組み
- 撮影
- 編集
- プレビュー
- 承認作業
- 公開
- アフターフォロー
これら以外にも膨大で、公開してからがはじまる作業というのも実に多い。映像編集が終わってから、映り込んでいる方々への公開承認作業も考えれば、まず100%毎日動画更新など不可能です。
裏側のワークフローは、とてつもない工数でパブリックなっていて、公開されている表面なんてほんの一部なんですよね。映像制作会社って普通に何日もスタジオで徹夜しているって知っているのかな??フジテレビなんて寝る部屋までありますが、役場なんて17時に閉めるわけでしょ?
しかも、その映像は、必ずしも良い影響だけ・・・とはいかないだろう。良いと思ってやったことが、必ずいつか問題になる日が来るのです。
地域おこし協力隊募集要項から読み解くもの
移住者にとっては、移住を検討している時間より、移住してからの方が長くなるケースもある。
だからこそ、最初から嘘のない要項を掲げ、要件変更をせずに、募集PRをしていかなければならないはず。
移住後に想定される問題に、事前にフォーカスして、幾通りもの解決シュミレーションを経て、それを協力隊が実行するような募集をしなければ、小さな過ちが大きな問題を生み起こすでしょう。
移住後のフォロー伝えることで、移住者を放置をしないことを宣言すればCVRも必然的に上がるだろう。
もし、自分が役場の長だったら・・・
もし自分が市町村の長だったら、地域おこし協力隊の活動として目標にすることは、
「この町の地域おこし協力隊は全員月収100万円を超えさせる目標を掲げてもらい、募集要項は隊員にビジネスをしてもらうこと、どんなビジネスか自由に選択していただいて住民と役場と力を合わせてそのサポートに徹します」
と言えることを、サポートするし目標にするとも思います。
第一、都会からきて地方にいって貧しくさせてどうする?
地域をおこすということ、地域社会の変革を重要な目標にするということは、ソーシャルレボリューション・ソーシャルイノベーションが重要であり、そもそもその土地に根付く価値の再発見と告知です。
ってそれ、いまITの聖地シリコンバレーで行われていることに非常に似ていることで、本当にエネルギーを持って地域創生にあたれる人材というのは、はっきり言ってビジネスマンではないでしょうか?
柔軟な発想アイディアもライブ感をもって実現する必要があるし、経営センスもかなり必要。
長年音楽業界にいた僕の見方からすれば地域おこし協力隊とは、「ALL AREA PASS」です。
地域のために活躍したいというミッションと想いの元、その町の、住民、経営者、誰とでも会える橋渡し的な存在なのだから、とてつもないビジネスチャンスをフリーパスで得ているという、なんとも羨ましい状況です。
役場の需要判断にありがちな、人手不足を補うことだけにとどめることはあまりにも勿体無い。
戦国時代の再来に気づけない人々
戦国時代とは、秩序が乱れて、互いに何かから何かを守りあう交換状態。
地域の良いところだけ偏って伝えても移住者は生まれ、その移住者が移住先で自殺するケースも今後あるだろうし、想定すべきですし、もう起きているのかもしれない。
村ほど横につながり、どんぐりの背比べの派閥が存在するが、移住者にとっては、縦軸の組織に守られないことに違和感を感じるだろう。
地方自治体が、下手な移住PRを打って、実際とPR内容が乖離していれば、それは必ず地元に天罰として帰って来るものであり、移住して来る人間に地域を破壊されていく構図にもなることも危惧していかなければならない。
全てではないが、地方自治体の間違った磁力や指示で、地域PRを目にすることが今後増えるのだろう。逆に一方で大成功する事例もあると思います。
結局なにもやらないで、ご先祖様や今与えられているものの理解を深め、丁寧に後世に伝え、他人のものを奪わずに、謹む心を抱き、足るを知るとして生き、自然を尊び、自然な暮らしをしていれば良かった、みたいになる可能性もあるだろう。
移住先のメリットや特色を見極める
それぞれの地域が抱える課題。
ある町にとっては人口減や後継者問題を課題として、ある村にとっては基幹産業など発展や展望を課題としている。
私は、BIASTRAで、移住者の増加への貢献に評価を受けた2017年以降、その影響力には手放しで喜ぶというより、逆に移住者の心配をメディアの責任感として感じ始めています。
もし自分が無責任な情報配信を行っていて、村や町の良いところばかり伝えているなら尚更のこと。
もちろんそんなことはないが、真実のメディアとは、実際の暗黒面を伝えることも責務として役割にある。
何を信じるかも、どこに移住するかも、PRされる側の読む側の自己責任ですが、だがしかし、配信する責任は計り知れない。
もし地域おこし協力隊として活動し、情報配信する側になる時は、著作権侵害など罪を伴うこともある。良い情報を届けることの難しさにも対峙する時が来る。配信した反応が想定の真逆のことも多々ある。
色んな人がいるから面白いよね。みんな違ってみんないい。相田みつを的な。
これをまとめようとする、「しまブロ」もまた、大きな課題と責任を背負っている。
最後に・・・
最後まで長文のグチをお読みくださりありがとうございます(いや、ごめんなさい)
役場って大変なのでしょうね。。。
募集要項を見ていただけなのですが、本当にかわいそうに思います。
地域おこし協力隊は、準職員のようですが、住民として大切に受け入れてくださいね。
ありがとうございました。